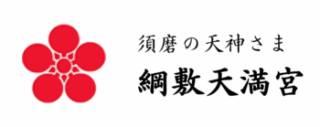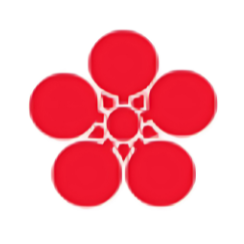
御祭神
菅原道真公は、承和十二年に京都で生まれ、
幼名を阿呼(あこ)と申されました。
幼い頃より学問に秀で、
五歳で和歌を詠むなど才能を示されました。
三十三歳で文章博士となり、
学問と政治の道に尽力されましたが、
藤原氏の讒言により太宰府へ左遷されます。
流謫の地でも人々を導き、
詩歌を詠みながら天に誠を尽くされ、
五十九歳で生涯を終えられました。
その清らかな心と学問の功績を讃え、
全国に天満宮が建立され、
学問の神・天神さまとして広く信仰を集めています。

ご由緒
歴史

菅原道真公が太宰府に左遷され、九州へ向かわれる途中のこと。海が荒れ、航海を続けることができず、やむなく須磨の浦へ避難されたと伝えられています。
そのとき、地元の漁師たちは大きな網の綱を使って「円座」を作り、道真公はその上でしばしお休みになりました。
この故事にちなみ、道真公の御没後七十六年にあたる天暦九年(955年)、当時の国府の命により綱敷天満宮が創建されました。
当社の境内には、この円座を模した「綱敷の円座」を再現し、訪れる人々に道真公のご遺徳と、この地にまつわる由来を静かに伝えています。
二十五霊社の一つ

二十五霊社(にじゅうごれいしゃ)とは、全国に数多くある天満宮・天神社の中でも、特に菅原道真公の御神霊を深く祀る由緒正しい二十五社を指します。これらは、北海道の名付け親として知られる探検家・松浦武四郎が、道真公への篤い信仰心から選定したものです。武四郎によって、二十五霊社には神鏡が奉納されています。
二十五霊社は、道真公の生涯や信仰、伝承にゆかりの深い神社であり、それぞれが道真公の御魂を慰め、その徳を仰ぎ奉る場として古くから特別な崇敬を集めてきました。天満宮の中でもとりわけ格式が高いとされ、当社はこの二十五霊社の一社に数えられ、学問の神様を祀る名社として広く信仰を集めています。
当社では、武四郎に奉納された神鏡をあしらった御朱印も頒布しております。
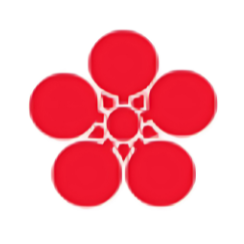
末社

稲荷社
御祭神 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)
商売繁盛の神様
京都伏見稲荷大社より勧請
厄神社
御祭神 八幡大神(はちまんおおかみ)
厄除けの神様
石清水八幡宮より勧請
諏訪神社
御祭神 建御名方命(たけみなかたのみこと)
勝負の神様
弁天社
御祭神 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)
諸芸能・縁結びの神様
白蛇社
金運の神様